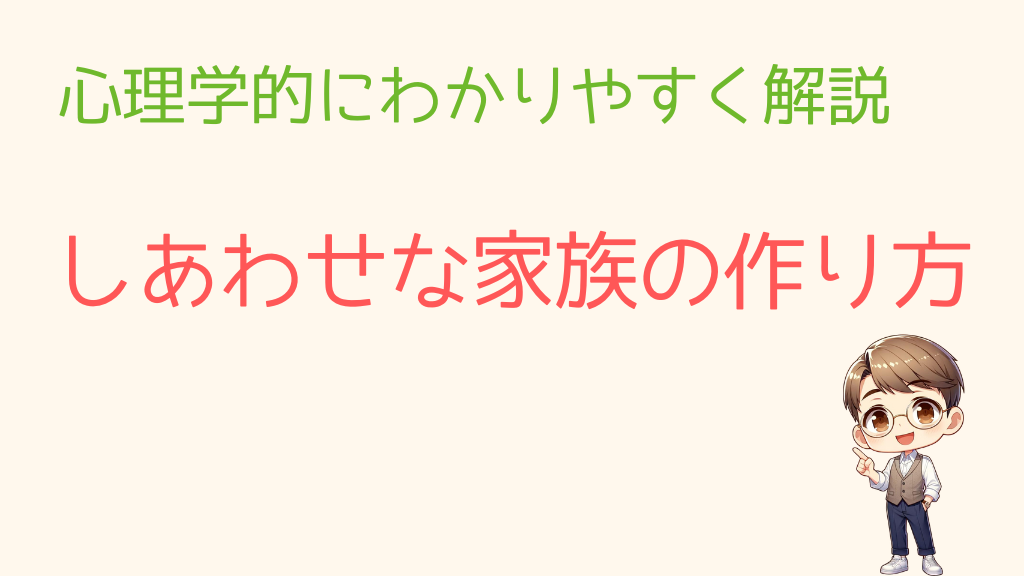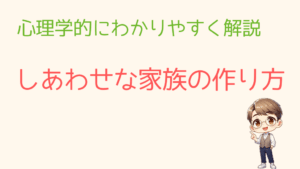「不登校の原因はゲームのせいだ」と親が言えば、「違う、学校のせいだ」と子どもは反論する。お互いの意見が平行線のまま、言い争いが繰り返されていませんか?
実はこの対立の根底には、確証バイアスという思考の罠があります。これは、自分の信念を補強する情報だけを集め、反対の情報を無視してしまう、人間の思考のクセです。
親は「育て方の失敗ではない証拠」を集め、子どもは「自分は悪くない証拠」を集める。お互いが自分の正しさを証明しようとするほど、本当の原因は見えなくなり、親子の信頼関係は壊れていきます。
この記事では、公認心理師の視点から、確証バイアスが親子のコミュニケーションをどのように破壊するのか、そして中立的な視点を取り戻し、建設的な対話を始めるための具体的な方法を解説します。
対立を終わらせ、お子さんとともに本当の解決策を見つけましょう。
親子対立の根源:確証バイアス(Confirmation Bias)とは?
確証バイアスとは?(自分の思い込みを支持する情報だけを集めてしまう心のフィルター)
確証バイアス(Confirmation Bias)とは、自分の信念や仮説を支持する情報だけを選択的に集め、反対の情報を無視したり軽視したりしてしまう、人間の思考のクセです。心理学では「Confirmation Bias」と呼ばれ、誰もが持っている認知の歪みです。
わかりやすく例えるなら、「見たいものだけを見るフィルター」や「都合のいいメガネ」のようなものです。赤いメガネをかければ世界は赤く見え、青いメガネをかければ青く見える。自分の信念というメガネを通して世界を見ているため、現実が歪んで見えてしまうのです。
不登校の場面では、この確証バイアスが親子双方に働きます。親が「ゲームのせいで学校へ行けなくなった」と信じている場合、ゲームと不登校を結びつける情報ばかりを集めます。一方、子どもが「学校の人間関係が原因だ」と信じている場合、学校での嫌な出来事ばかりを思い出します。
公認心理師の視点では、これは親子の悪意や頑固さではなく、人間の脳が持つ自然な反応です。しかし、この思考のクセが対立を生み、本当の問題解決を妨げてしまうのです。
なぜ不登校問題で親子の確信が固定化しやすいのか?
確証バイアスが不登校の場面で特に強く働くのには、心理的な理由があります。
親御さんにとって、不登校は「自分の育て方が間違っていたのではないか」という不安と直結します。この不安から自分を守るために、「育て方の問題ではない」という信念を強く持とうとします。そして「ゲーム依存が原因」「学校の環境が悪い」「思春期の一時的な反抗」など、自分の育て方以外に原因を求める情報を集めるのです。
一方、お子さんにとって不登校は、「自分がダメな人間だ」という自己否定につながりかねません。この自己否定から自分を守るために、「自分は悪くない」という信念を持とうとします。そして「先生が理解してくれない」「クラスの雰囲気が合わない」「親が厳しすぎる」など、自分以外に原因を求める情報を集めるのです。
公認心理師の臨床経験では、親子双方が「自分を守りたい」という心理から、それぞれの確信を強めていくケースが非常に多く見られます。この防衛的な心理状態が、確証バイアスをさらに強化するのです。
さらに、インターネットやSNSの普及が、この問題を悪化させています。検索すれば自分の信念を支持する情報はいくらでも見つかります。「不登校はゲームのせい」と検索すれば、それを支持する記事が並びます。「不登校は学校が悪い」と検索すれば、学校批判の情報が出てきます。簡単に自分の信念を補強できる環境が、確証バイアスからの脱却をより困難にしているのです。
互いの「正しさ」を主張し合う不毛な対立
確証バイアスの最も厄介な点は、お互いが「自分は正しい」と確信していることです。
親は集めた情報に基づいて「ゲームを制限すれば学校へ行けるはずだ」と考えます。子どもは自分の経験に基づいて「学校の環境が変わらなければ行けるわけがない」と考えます。どちらも自分なりの根拠を持っているため、相手の意見を聞く余裕がなくなります。
この状態で対話をしても、建設的な話し合いにはなりません。親の提案は子どもに「問題をわかっていない」と拒絶され、子どもの訴えは親に「責任逃れ」と受け取られます。結果として、お互いの距離は開き、解決への道は遠のいていくのです。
確証バイアスが引き起こす親子のコミュニケーション不全
【親への影響】 一方的な原因追及と子どもの心境の見落とし
親御さんが確証バイアスに陥ると、一方的な原因追及が始まります。
「やっぱりゲームばかりしているから学校へ行けないんだ」という信念を持つと、お子さんのゲーム時間ばかりが目につきます。深夜までゲームをしている姿、朝起きられない様子、ゲーム以外の活動への無関心。これらの情報が次々と集まり、「ゲームが原因だ」という確信が強まります。
しかし、この確信が強まるほど、他の可能性が見えなくなります。お子さんが学校で友人関係に悩んでいる可能性、感覚過敏で教室の環境が苦痛である可能性、学習の遅れに不安を感じている可能性。これらのサインは、「ゲームのせい」という思い込みのフィルターに遮られ、見落とされてしまうのです。
公認心理師の視点では、不登校の原因は単一ではなく、複数の要因が複雑に絡み合っていることがほとんどです。ゲームが逃避先になっているとしても、それは結果であって原因ではないケースも多いのです。しかし確証バイアスが働くと、この複雑さが見えなくなります。
さらに問題なのは、親の一方的な原因追及が、お子さんを追い詰めることです。「ゲームをやめれば学校へ行ける」と言われても、本当の苦しみがゲーム以外にある子どもにとって、それは「わかってもらえない」という絶望につながります。
<ここに確証バイアスによる見落としの具体的な事例を挿入>
【子どもへの影響】 親の励ましすら「社交辞令」と解釈してしまう
確証バイアスは、お子さん側にも深刻な影響を与えます。
お子さんが「自分はダメな人間だ」「誰も自分をわかってくれない」という否定的な信念を持っている場合、親御さんの温かい言葉や励ましも、その信念を通して解釈されてしまいます。
親が「あなたは頑張っているよ」と言えば、「本心では私をダメだと思っているのに、社交辞令を言っている」と受け取ります。親が「ゆっくり休んでいいよ」と言えば、「諦められた。もう期待されていない」と解釈します。親が「何か困っていることはない?」と聞けば、「責められている。何か答えなければ」とプレッシャーを感じます。
公認心理師の臨床では、「親の言葉は全部嘘に聞こえる」「何を言われても責められているように感じる」と語るお子さんに多く出会います。これは親御さんの言い方や態度の問題ではなく、お子さん自身の確証バイアスが、親の言葉を否定的に変換してしまうのです。
このバイアスが働くと、親子のコミュニケーションは完全に機能しなくなります。親がどんなに誠実に接しても、その誠意は届きません。お子さんは「どうせわかってもらえない」という確信を強め、心を閉ざしていきます。
さらに、お子さんが持つ「学校が悪い」「先生が悪い」という信念も、確証バイアスによって強化されます。学校での良い出来事は記憶から消え、嫌な出来事だけが鮮明に残ります。本来であれば解決可能な問題も、「学校は変わらない」という諦めによって、改善の機会が失われてしまうのです。
公認心理師が教える:「思い込みの罠」から抜け出す対話と行動
ステップ1:自分の「絶対の確信」をあえて疑う「反証思考」
確証バイアスから抜け出す第一歩は、自分の信念を意図的に疑うことです。
以下の「反証思考」ワークを試してみましょう。ノートに書き出すことをおすすめします。
まず、あなたが信じている不登校の原因を書きます。例:「ゲームのせいで学校へ行けない」
次に、「もしこれが間違いだったとしたら」という前提で、他の可能性を少なくとも5つ書き出します。
- 学校での人間関係に問題があるかもしれない
- 学習の遅れに不安を感じているかもしれない
- 感覚過敏で教室環境が苦痛かもしれない
- 朝の体調不良に身体的な原因があるかもしれない
- 将来への漠然とした不安を抱えているかもしれない
この作業は、決してあなたの最初の考えを否定するためではありません。視野を広げ、見落としていた可能性に気づくためです。
公認心理師の視点では、この反証思考は認知行動療法の基本的な技法です。自分の思い込みを相対化し、柔軟な思考を取り戻すために非常に有効なのです。
同じワークを、お子さんの視点からも行ってみましょう。お子さんが「学校のせいで行けない」と言っている場合、「もし学校以外にも原因があるとしたら」という前提で、他の可能性を考えます。
- 生活リズムの乱れが影響しているかもしれない
- 家族関係のストレスがあるかもしれない
- 自己肯定感の低さが背景にあるかもしれない
この練習を続けることで、一つの原因に固執せず、複数の可能性を検討する習慣が身につきます。
ステップ2:情報の出どころ(ソース)を冷静に見極める習慣
確証バイアスを強化する大きな要因は、感情的に情報を集めることです。
不登校に関する情報を探す時、どのような情報源から得ているか振り返ってみましょう。個人のブログやSNSの投稿、匿名掲示板の意見など、感情的で偏った情報ばかりを見ていませんか?
公認心理師の視点では、中立的で信頼性の高い情報源を意図的に選ぶことが重要です。具体的には以下のような情報源を優先しましょう。
- 公認心理師や医師など、専門的な資格を持つ人の執筆・監修記事
- 公的機関(文部科学省、厚生労働省等)が発信する情報
- 学術研究に基づいた書籍や論文
- 複数の視点を公平に紹介している記事
逆に、以下のような情報は慎重に扱う必要があります。
- 「絶対にこれが原因」と断定している情報
- 特定の方法だけを唯一の解決策として宣伝している情報
- 個人の体験談のみで専門的根拠がない情報
- 感情的な表現や極端な主張が多い情報
情報を集める際は、「これは自分の信念を補強するために選んでいないか?」と自問する習慣をつけましょう。意図的に、自分の考えと異なる視点の情報も読むことで、バランスの取れた理解が得られます。
ステップ3:互いの「確信」を尊重し、建設的な「事実確認」を行う対話法
お子さんとの対話で確証バイアスから抜け出すには、互いの主張を否定せず、事実ベースで話し合う技術が必要です。
以下の対話法を試してみてください。
まず、お互いの「確信」を一度受け止めます。親が「ゲームのせいだと思う」、子どもが「学校のせいだと思う」という主張を、否定せずに受け入れます。
次に、「事実確認」のための質問をします。感情や判断を交えず、具体的な事実だけを聞きます。
親からの質問例:
- 「学校で具体的にどんなことが辛いの?今週あった出来事を教えてくれる?」
- 「朝起きられない時、体はどんな感じがするの?」
- 「ゲームをしている時はどんな気持ち?」
子どもからの質問例(親が促す):
- 「お母さんはなぜゲームが原因だと思うの?具体的に何を見て心配になったの?」
公認心理師の視点では、この事実確認の対話が、お互いの思い込みを解く鍵になります。抽象的な主張ではなく、具体的な事実を共有することで、見えていなかった側面が明らかになるのです。
また、対話の中で「お互いにそう思う理由を教えてくれる?」という言い方も効果的です。相手の考えを否定せず、その背景にある理由を理解しようとする姿勢が、信頼関係を修復します。
最後に、「どちらが正しいか」を決めるのではなく、「一緒に事実を集めよう」という協力関係を築くことが重要です。「私はゲームが原因だと思うけれど、あなたは学校が原因だと思うんだね。じゃあ、両方の可能性を考えながら、もっと詳しく状況を見ていこう」という姿勢が、対立を終わらせる第一歩になります。
【最終導線】親子間の「情報戦争」を終わらせる専門家の役割
確証バイアス克服に第三者による「中立的な交通整理」が不可欠な理由
ここまで読んで、「対話が必要だとわかっても、実際には難しい」と感じている方も多いのではないでしょうか。
それは当然のことです。なぜなら、親子双方が強い確信を持っている状態で、感情を抜きにして冷静に対話することは、非常に困難だからです。
親御さんにとっては、お子さんの将来への不安や、自分の育て方への疑念という強い感情があります。お子さんにとっては、親に理解されない孤独感や、自分の苦しみが軽視されているという怒りがあります。この感情の渦中で、客観的な事実確認を続けることは容易ではありません。
公認心理師の視点では、このような状況で最も有効なのは、第三者による「中立的な交通整理」です。専門家は親子のどちらの味方でもなく、問題解決のための協力者として、以下のような役割を果たします。
- 親子双方の主張を公平に聞き取る
- 感情と事実を切り分けて整理する
- 見落とされている可能性を提示する
- 対立を協力関係に変換する対話を促進する
専門家がいることで、親子は「どちらが正しいかを証明する場」ではなく、「一緒に解決策を探す場」として対話できるようになるのです。
公認心理師による「中立的な視点」が親子対立を解消する
ぜんとカウンセリングでは、不登校に特化した公認心理師が、親子双方の確証バイアスを整理し、建設的な関係を築くサポートをします。
カウンセリングでは、まず親御さんとお子さん、それぞれの「確信」を丁寧に聞き取ります。どちらの主張も否定せず、その背景にある感情や経験を理解します。
その上で、親子双方が見落としている可能性を提示します。親が考える原因、子どもが考える原因、そしてそれ以外の可能性を公平に検討し、より正確な状況把握を目指します。
また、親子別々のセッションと、家族合同でのセッションを組み合わせることも可能です。別々のセッションでは、お互いに言いにくいことを安心して話せます。合同セッションでは、専門家の進行のもと、感情的にならずに事実確認を進められます。
ぜんとカウンセリングでできること:
- 親子双方の「思い込み」を中立的に整理
- 見落とされている要因の発見と共有
- 対立から協力への関係転換のサポート
- 事実に基づいた具体的な解決策の提案
もう原因探しで親子がぶつかるのは終わりにしませんか?公認心理師が中立的な立場で、あなた方の「思い込み」を整理し、解決への協力関係を築きます。
ひとりで抱え込まないでください。確証バイアスは、当事者同士では気づきにくく、抜け出しにくいものです。専門家の客観的な視点が、対立を終わらせ、本当の解決への道を開きます。
ぜんとカウンセリングは、親子の信頼関係を取り戻し、一緒に前に進むためのサポートをします。
[ぜんとカウンセリングに相談する]
まとめ
親子で不登校の原因について意見がぶつかるのは、確証バイアスという思考の罠が原因です。親も子どもも、自分の信念を守るために都合の良い情報だけを集め、お互いの視点が見えなくなっています。
この対立は、悪意や頑固さからではなく、誰もが持つ思考のクセから生まれています。自分の確信を意図的に疑い、情報源を冷静に選び、事実ベースの対話を心がけることで、確証バイアスから抜け出せます。
しかし、感情の渦中にいる親子が、一人で客観性を保つことは容易ではありません。第三者である専門家の中立的な視点が、対立を終わらせ、協力関係を築くために不可欠です。
あなたの信念も、お子さんの信念も、確証バイアスによって固定化しているかもしれません。対立を終わらせ、一緒に真の原因を探しましょう。お子さんとの信頼関係は、今日から取り戻せます。
FAQ(よくある質問)
Q. 確証バイアスは誰にでもあるものなのでしょうか?
A. はい、確証バイアスは人間の脳が持つ普遍的な思考のクセで、誰にでもあるものです。自分の信念や価値観を守るために、それを支持する情報だけを集め、反対の情報を無視してしまう傾向です。不登校の親子だけでなく、政治、科学、日常生活など、あらゆる場面で働きます。専門家であっても、自分自身のことになると確証バイアスに陥ることがあります。これは知性や性格の問題ではなく、人間の認知の仕組みそのものなのです。
Q. 子どもの主張を尊重しながら、親の考えも伝えるにはどうすればいいですか?
A. まず子どもの主張を最後まで聞き、その考えに至った理由や感情を理解することが大切です。その上で、「あなたの考えはよくわかった。私はこう思うんだけれど」と、自分の考えを押し付けず提案する形で伝えます。公認心理師の視点では、重要なのは「どちらが正しいか」ではなく、「お互いの視点を知り、一緒に考える」という姿勢です。「私はゲームが影響していると思うけれど、あなたは学校のことが辛いんだね。じゃあ両方の可能性を考えてみようか」という言い方が効果的です。
Q. 自分の考えが確証バイアスかどうか、どうやって見分ければいいですか?
A. 以下のサインがあれば、確証バイアスが働いている可能性があります。自分の考えと異なる意見を聞くと、すぐに否定したくなる。自分の信念を支持する情報ばかりを集めている。「絶対に〜だ」「間違いなく〜だ」と断定的に考えている。他の可能性を考えることに抵抗を感じる